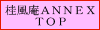
|
幼稚園では、基本的には文字指導はしなくてもよいのです。けれども、多くの幼稚園では、 文字教材を購入しています。これは、幼稚園でも文字を書くことへの指導の要望がある証拠ですね。 幼児期に、これほど文字の読み書きがおこなわれているにもかかわらず、幼児教育の研究においては、 文字を書くことの研究がありません。 幼稚園の先生方は、大学では文字の教え方を習っていない上に、現場では指導マニュアルがないため、 手さぐりで指導をされています。ですから、指導にはたえず不安を持っておられます。 それは、保護者も同じです。見よう見まねで文字を書きはじめたわが子に、どのようなアドバイスをして よいかわからない、間違いは、いくら注意しても直らない。 文字に全く関心がないのが不安でたまらない、などなど・・・ 要するに、すべての不安の原因は、幼児向けの文字の情報があまりにも少ないことです。 それならば、「まず情報を発信することから始めよう。」ということで、広島市の、井口ルンビニー幼稚園では、保護者にお願いして、「子どもたちが文字を書くことに関してどのような考えを持っているのか」ということのアンケートをとり、それをもとに、幼児期にはどのような教え方をするのがよいのか、どこまで教えておけばよいのかを考えてゆくことにしました。 その第一弾として、保護者からの回答を分類し、項目を立てて『保護者の声』として掲載しました。 『保護者の声』は原文のままです。それぞれの項目で、私の長年の経験からのコメントを付けています。 ぜひともお読みください。 なお、【研究ノート】として別に分析と考察を行っております。関心のおありの方はこちらもお読みください。 こちらをクリック→〈入学前の文字指導の在り方〉『保護者の声』における分析と提言 |
|
(1)書写指導はいつから開始するべきか 〔指導における贊否〕 (以下の回答はすべて、原文のままです) (年長) ・幼稚園で客観的に指導いただけると助かります。 ・年長になってかきかたが始まるけど年中から始めてもらえるとよかったかもしれない。 ・園で努力してくれるのでおやとしては安心です。 ・親が何度言っても自分なりに書いていた子が正しく書けるようになった事は 来年小学校といういろんな期待や不安がある中とてもありがたく嬉しく思いました。 たのしく学ぶきっかけを集団の中で教わることは大切なことだと思います (年中) ・年中になってようやくひらがなが読めるようになったばかりで まだまだこれから教えることだらけです。幼稚園で指導して頂けるのはとても心強いです。 ・書き方について幼稚園で御指導いただけるのはすごく嬉しいです。 「読む」ことはすぐにできたのですが、なかなか「書く」ことが上達できずにいます。 ・いつもおせわになっています。幼稚園でひらがな等の練習を経験していると 小学一年での文字の練習がスムーズに移行できますので、重点課題として園が取り組んでいただける事、とても感謝しています。 〔指導上の不安〕 (年長) ・親自身が持ち方に自信がないため教えることができない ・(親が)気にしたほうがよいorしないほうがよいことについてアドバイスが頂けるとうれし いです。 ・今まで全くかけないこどもは素直にすんなり入っていけてヘンなくせがつかないと聞いていますが・・・ ・園では50音順で書いているのですか?それとも簡単な字から書き始めているのでしょうか?! ・小学校に入学するまでに自分の名前がきれいに書けるようになってくれたらと思う (年中) ・ ・・・本人が書きたいように書くので違うよ、こうだよと直そうとしても聞かないことがあります。 ですから園などで他のよい子さんと一緒に出来たら素直にできるのでは・・・という期待もあります。 ・先生方に教えて頂くのが子どもにとっては一番身につく方法だと思いますが、家でも同じように指導できれば よりよいと思いますので親も教材に触れたり注意点などがわかると良いのではないでしょうか。 ・家の方でも少しずつ文字を読む練習をしているのですが、なかなか覚えられないようです。 お友達の中にはすらすら本を読める子も文字を書ける子もいてかなり親があせりを覚えますが まだ文字に興味が持てないのかと思い少しずつでも覚えて欲しいと気長に取り組んではみています。 本が好きでも読んでもらうのが大好きでどうも自分で読むという感じになってません。 ・うちでもワークブックをさせることがあるのですが、ただなぞったり、 お手本を見て書くだけのものではすぐあきてしまうみたいです。 【コメント】 年長と年中の意見を比較すると、年長の方がより具体的になっていますね。 それだけ、年長になりますと切羽詰まったものがあるからです。 「教えなかったことでの焦り」 「教え方がわからないことの不安」「教えても身につかないことの不安」「注意しても直そうとしないことへの苛立ち」 など、入学が目前になりますと、よけい いらいらがつのりますね。誰も、不安を解消してくれないからです。 それで、子どもたちについつい八つ当たりをしてしまうようになります。 回答の中には、不要な不安や苛立ちが、ずいぶんとありました。 子どもたちの書き方を見ておりますと、「親の教え方が間違ってるなあ。」と思うことがよくあります。それと同時に、教材(ワークブックやドリル)の与え方がよくないのではないかと思います。 どのような時期に、どうやって教えたらよいかという目安がないこと、困ったときに適切なアドバイスを聞くことができないことが、このような不安となるのでしょう。 |
|
(2)姿勢・執筆についての意見 (年長) ・鉛筆の持ち方や姿勢がだんだんと崩れてくる ・字を覚えることもたいせつなのですが・・・小学校の先生が口をそろえておっしゃることは、 エンピツの持ち方が正しくなくて矯正できないくらい身についてしまっているということです。 まずは、エンピツを持ちいろいろな線をたくさん書いていくことで (横線、縱線、はらい、はね、曲線)楽しみながら正しいエンピツの持ち方を身につけていくページを たくさんとりいれてみるのはどうかと思います。 家庭で身についたエンピツの持ち方の矯正を園でするのは大変かとは思いますが、 園だからこそ素直に子供たちが受け入れられるのではないでしょうか。 ・上の子で実感したのですが、注意をすれば治るけど、見ていないと姿勢が崩れてしまう、ということです。 自分で見ていたころは気になりませんでしたが、習い始めてお任せしていました。 学級の参観であまりにも姿勢が悪くて驚きました。 やはり細かい所までとなると少人数制でないと難しいかな?と思いました。 ・鉛筆の持ち方、姿勢については小さい時にしっかり身に付けてほしいところです。 ・鉛筆の持ち方も気になりますが、姿勢が悪く 目が近くなり気になっています。 気が付いた時は注意するのですがクセになっているようです。ご指導いただけたら幸いです。 ・子どもたちの鉛筆の持ち方が悪くて困っています。持ち方が悪いと姿勢まで悪くなり、 家でも何度も繰り返し注意していますがなかなか直りません。 特にルンビニー卒園児の兄と姉はあまりひどいもちかたにびっくりさせられます。 一度ついた持ち方はきょう正出来ないのでやはり最初がかんじん?と思ってしまう今日この頃です。 ・書き方教室でお世話になっております。娘は文字を書くのは好きですが姿勢が悪く文字の書き順はもちろんの事、 よく鏡字になってしまっているのに"別にいいじゃん!"と気にしていません。 なるべく正しい姿勢で書くように注意していますがなかなか直りません。 書き方教室へ通い始めて意識出来る様になるのを期待しております。 (年中・年少) ・家でひらがなの練習はしていますが書き順とえんぴつの持ち方を教えることが難しいと思います。 持ち方はどうしても"くせ"があるみたいで何度言ってもなかなかです・・・ すでに幼稚園でも少し習ったのか時々は「えんぴつはこう持つんだよねー」 と正しい持ち方をしてみせてくれる事もあります。クラスのみんなで練習すると正しい持ち方になるのではと 期待してしまいます・・・ ・字を書き始める時、姿勢と丁寧に書くことは教えたつもりなのですが、これもなかなか・・・です。 どうぞよろしくお願いします。 ・以前"公文"で扱っている鉛筆や色鉛筆を見たことがあります。三角形で短めの長さ・・・ 幼児から小学校低学年用に作られていて、確かに子どもにも扱いやすく、 何よりも正しい持ち方が習得出来ると感心しました。一般でも購入できるらしいので購入する予定です。 まずはどんな鉛筆が良いか検討してみるのも良いではないでしょうか。 ・まずはどんな鉛筆が良いか検討してみるのも良いではないでしょうか。 【コメント】 “鉛筆の持ち方”や”姿勢”に対しての意見はとても多く、親の関心事であることはよくわかるのですが・・・ 今のような文字の書かせ方をしていれば、どちらもなおりません。 現在市販されている文字教材だけでは、姿勢も鉛筆の持ち方も直りません。親が言って聞せても、幼稚園で言って聞かせても、その場限り。放っておくと、“自然に”悪くなるのです。多くの場合、子どもたちの指は、鉛筆をうまく持てるほど器用ではなく、姿勢良くして書けるほどゆとりはありません。 鉛筆の持ち方が悪いのは、正しい持ち方では書きにくいからです。鉛筆は本来、指先で持つものですが、 幼児は指の器用さがまだ充分でないので指先だけではうまく持てません。ですから、ぎゅっとにぎりしめて鉛筆を 安定させます。この持ち方では、姿勢良くした状態では指がじゃまをして、手元が見えません。 それで身体を傾けて手元を見ます。だから姿勢が悪くなります。 さらに、鉛筆をぎゅっとにぎりしめただけではまだ不安定なので、机にすがりついて安定をはかります。 ますます姿勢が悪くなります。 鉛筆をぎゅっとにぎりしめると指や身体に力がはいってしまうため、指が痛くなったり、 すぐに疲れてしまいます。 “鉛筆の持ち方”と”姿勢”の躾はニワトリとたまごのような関係で、持ち方が悪いから姿勢が悪くなる、姿勢が悪いから持ち方が悪くなる、という悪循環をします。 ではどのような解決法があるのでしょうか。 アンケートの回答にありますように、用具の選び方は大切です。 太い鉛筆がよいことは、ずいぶん前から言われています。でも普及していませんね。この鉛筆がよいことはわかっているのですが、すぐに手に入らない、削りにくい、目をはなすと子どもたちは、身の回りに大量にある普通の鉛筆で字を書く、など良いとわかっていても使い勝手の悪い用具でもあるのです。 鉛筆の工夫、持ち方を直す補助器具は一時期色々考えられましたが、いずれも大ヒット商品になっていないのは、子ども自体が必要としないこと、持ち方が身につくまでそれを与え続ける大人の根気がないからです。 私の教室でもいろいろな工夫をしていますが、持ち方の悪い子ほど、必然性が理解できないので、このような用具をいやがります。 幼稚園や習字教室で鉛筆を持たせるのは僅かな時間です、それ以外に遊びの中で文字を使用したり、習い事で文字を書くことが多くなりますと、文字を書くことで精一杯で、持ち方への意識はほとんどなくなります。 持ち方や、姿勢に関しては、早く指導すれば完了するというものではありません。やはり、小学校に入ってからの指導が大切です。 そして、習慣として身につくまで指導し続ける根気が必要です。 |
|
(3)運筆において気になること (年長) ・「あ」「め」などまるくかく文字が見ながらでも書けないみたいです ・はねや、はらいや丸みを持たせるところ、とがらせるところなどの区別が覚えられない ・お手本を見ながらていねいに(おちついて)書く姿勢がなかなか身につかない ・書く方向が混乱することがある。(下から上 右から左) ・便せんなど線の上にきちんとならべて書くのが苦手 ・幼稚園ではとめ、はね、はらいなどは教えてもらえるのか。 ・ただしく持っていれば右小指の裏から手首あたり(図)が汚れるはずです。 ここを付けて移動する動きを取り入れある程度慣れてから鉛筆を持たせてみるというのはどうでしょうか? ・とめやはらいの区別がむずかしくて理解してないようです。 ・姉と本人、二人を見ていて思うのですが、きれいに書こうとすると、2Bをつかっていてもものすご~く力が入ってて、 どうか?と思います。ついでに姿勢もわるくなっているし。 (年中) ・次の段階で"る"などくるりと書く文字を書き始めたのですがこのくるりが意外と難しいようです。 そこで"る"は数字の"3"の最後をくるりとするんよとおしえたりするんですがまちがっているでしょうか? 正しくは"る"ですから、字がくずれるかな・・・と思ったりします。 ・上の子で気がついたのですが、ひらがなから止めはらいをきちっと教えていれば漢字でつまづくことがなかったの かなとおもっています。 【コメント】 手本の通りに書けないのは、字形の認識の発達と指の機能的な発達が、まだ文字を書く 適齢期になっていないからです。ひらがなは、親が考えている以上に書きにくいのです。一文字の中で、線がいろいろな方向に変化しますからね。 公文のように、ステップアップしてゆく教材があればよいのですがそれが今のところありません。 現在の教材は、小学校1年生で使用するものと対して変わりがありません。 それを使わせて「なんで手本にとおりに書けないの!?」と困ったり、叱ったりするのですから、親も子も気の毒としか言いようがありません。 「ならば、どうしたら良いのですかッ!!!!」と、怒りの声が聞こえそうですね。 みんなで、怒りましょう!!要求をしましょう!!! 「どこへ言うんですか~?」 う~ん・・・困ったことですねえ・・・やり場がないとはこういうことですか・・・ 「一緒にがんばりましょう!」 個人的なご相談、ご意見は、当方までどうぞ。どうぞ、ご遠慮なく。 |
|
(4)筆順についての意見 (年長) ・自己流の書き順を覚えてしまっていて、教えようとしてもうるさがったりする ・かき順が違う ・しかしかけるようになっても、教えたつもりでも書き順が身につきにくい様に思われます. 園で教えてくださったおかげでうちは「ママ知ってる?こうやって止めてこっちが先に書くんよ。」 など私に教えてくれるようになりました。 ・書き順がばらばら ・以前、上の子が課外の書き方教室で指導をうけましたが、 その際人数が多かったためか書き順までみていただけなかったようで字は習得したものの、 書き順は自己流で覚えてしまいました。そこで、書き順をしっかり教えていただければ・・・と思います。 (年中) ・他にも鉛筆のもちかたや書き順もおかしいので楽しく学べる機会があると嬉しく思います。 ・書き順も横についていないと好きな順番に書いている様です。 お友達にお手紙をあげたいようなので上手に書けるようになれたらいいなと思います。 なぞって書ける透明シートのようなものはないのでしょうか? ・いつも大変お世話になります。とても嬉しいことです。年少から本人が興味をもち市販の ワークブックを買い与えるだけで独学で字を覚え書き始めました。鏡文字はないのですが、 書き順が違う字がいくつかあり、困ったなあとおもっていました。 まだ幼稚園なのでそこまで神経質にならなくてもいいかなあとも思いますが、あとから直すよりは、 正しく覚えた方がいいですよね。なかなか親の言うことは素直に聞けないようなので、 先生から教えていただけると助かります。 ・書き順も最初から教えておかないと途中で直すのは難しいみたいです。 ・市販のワークブックを購入してやらせてみたことがありましたが文字の書き順が理解できないようでした。 (1、2と番号がふってあるタイプでした)例えば書く順番ごとに色分けしたり、 書き始める場所のわかりやすいものがあるとありがたいと思います。 ・書き順が違ったりします。 【コメント】 ―直らない筆順― 筆順の指導は本当に難しいです。幼児にとっては必然性がないだけではなく、書きにくい順番でもあるのです。 「ま」・「も」はともに横線が2本あるのに、「ま」では先に書き、「も」ではあとから書きます。 「お」・「む」の点はさいごですが「な」・「や」では途中です。「う」・「え」もそう。点はあとからの方が合理的かも。 「わ・れ・ね」は長いたて線から書くのに、「た」・「な」・「や」は長いたて線からは書きませんよね。 余談ですが、今の筆順のルーツはご存じですか? ひらがなは漢字の草書という書体(今風に言えばフォントかな?)からできたもので、その漢字の筆順がそのままひらがなの筆順になっているのです。 この筆順は、現代では必ずしも書きやすさに直結していません。特に幼児にとっては、書きやすい書き順が正義であり、大人の決めた筆順は、なんら必然性のないことですから、 注意されても、ただうるさく感じるだけです。 当然と言えば当然ですが、それでは入学後に不都合が生じるわけで親は心配するのですが、当人はそれが理解できません。 ですから、目を離すと、自分が書きやすいように書いてしまいます。 子ども自身は、 ある程度の年令が来ないと、文字を正しく書く必要性がわからないのです。 100回書いて覚えた、間違った書き方は、100回正しく書かいて、ようやく元の白紙の状態になります。それからまた100回正しく書いて定着するということです。 その間ずっと元の書きかたをしないと言うことは考えられませんから、相当の根気がいります。 大人にとっては間違いであっても、自然に覚えたその書き方は、子どもにとって一番書きやすい書き方なのですから、 ついつい書いてしまうのも無理からぬ事。多くの場合、幼児期には文字を書いている最中には筆順にまで頭がまわりません。 遊びの中で書く文字は、とくに筆順には無意識になりがちです。とにかく根気よく言い聞かせるしか方法はありません。 |
|
(5)字形について (年長) ・鏡字を書くことが多い ・時々反転した文字を書くことがある ・文字の大きさがバラバラでまとまりがない ・字の大きさがバラバラ ・これはある程度長い期間一緒に持って形を整えることで改善できると思います。 先生ひとりではずっと特定の子ばかりというわけに行きませんから難しいと思います。 ・左右逆に書く ・他の書き方教室にかよっていますが、お手本の字が少しくずれて(起筆を大袈裟に書く等) もそのまままねて書くので困っています。 ・次に字については美しさ、字のバランスよりもとめ、はねなどの正確さを覚えてほしいところです。 バランスなどはおおきくなって自分で追求できるのではないかと思います。 ・文字の大きさをそろえて書けない (年中・年少) ・初めは字を大きく書いて練習するためか小さく書く事が難しかったりします。 【コメント】 「幼児期にそこまで心配しなくても・・・」と思うのは、経験者であり、「こんなにも気になる!」のが、 入学前の子どもがいる親の本音でもあります。 子どもに対する期待と不安によるものですが、やはり、情報が少ないことで、過剰反応してしまうのでしょう。 もっとも、こんなことを入学後にも、親がずっと気にかけてくれると、 期待通りのきれいな字になるのですが、なぜか入学後には文字を書くことに関心がなくなってしまうんですねえ。 「入学後には、それなりにいろいろと問題があるのだから、せめて文字を書くことだけでも、入学前にマスターさせておきたい。何とかならないのですか?!」というのが親の本音のようです。 そうは言われてもねえ~・・・ ぼやきはさておきまして・・・ ―鏡字― 鏡字を書くのはなぜかということについてはいくつか原因があげられてはいますが、 はっきりとした原因はわからないようですが、さほど気にすることではないようです。 幼児期に文字を書き始めたころにはよく見られるのですが、文字をくりかえして練習し ているうちに直っていきます。入学後の文字についての問題点としては特にあげられて いないようですし、私自身の経験からしてもいつまでも鏡字を書く子はいませんでした。 ―手本通りの字形が書けない、文字が不揃いなのはなぜかー 文字を書く年令にもよりますが、字形の把握が曖昧であることが原因の場合と、 鉛筆の持ち方あるいは書写速度が原因の場合があります。 文字は何本かの線の組み合わせですが、その組み合わせかたの認識が曖昧な子もいれば正確な子もいます。 線の長さや傾き、交叉している位置、丸いところのおおきさなどはアバウトになりがちです。 手指の機能が追いつかない場合もあります。 「の」「め」「あ」など斜め縱線から回転する部分はなかなか習得できません。 持ち方が良くないと、一定の範囲でしか鉛筆は動きません。それが字形や大きさに影響しているのです。 ―書写速度と字形― 文字をとても早く書く子がいます。文字の線の書き方は、 始筆→送筆→収筆(とめ・はね・はらい)という原則があるのですが、 鉛筆を持つ手が不安定な場合、書き始め(始筆)と書き終わり(収筆) がきちんとできません。そののため、本人は一生懸命書いているにもかかわらず、 落ち着きのない書き方、乱雑な書き方をしているように誤解されることがあります。 |
| (6)国語と書写―「文字のおけいこ」と「書き方のおけいこ」ー (年長) ・こおり→こうり おおかみ→おうかみ こおろぎ→こうろぎ などと思っている。 ・拗音(小さいや)、促音(小さいつ)がうまく書けない。 ・「さ」が「ち」のように点画がつづいていると読み間違えて「ち」と思い込んでしまいます。 ・ひらがなとカタカナの区別がついていない。 ・「は」と「へ」の二通りの読み方の使い方です。 ・不思議なことにつみきに書いてある少し大きな文字で遊んだりしているのですが個々には読めても、 いざ本を読もうとすると文字の大きさが違うだけで、別のものに見えるようで、読めなかったりします。 書体も本によって色々あるので読みづらいようです。 ・園でみんなでするのならともかく、家で、となるとあきないような色とりどりのものや文章の中での 書き方の勉強の方がよいのではと思います。 【コメント】 書き方の指導をしますというと、親はあれもこれも期待をするようですね。子どもたち自身も年長になると、カタカナや漢字も書きたがります。あれもこれも書かせることは可能です。でも、それがすべて正しく定着することはありません。1.2回の指導で定着するようなら、あちこちの学習塾がとっくに行っています。 ひらがな・かたかな・漢字あるいはことばの表記を正確に覚えさせることは「国語の学習」であり、「書き方(書写)の学習」は、正しく整った字を書かせること、長時間、文字を疲れないように書かせることではないでしょうか。年令があがっていくと言葉の学習(国語の学習)と書写の学習は同時に行えますが、幼児期には国語の学習(ことばを正しく書くこと)と、書写の学習(正しい書き方の学習)とは同時には行えません。文字を書くこと自体を徹底させるのであれば、切り離して行う方が効果的です。 たとえば、「あひる」ということばを書かせますと、子どもたちの頭の中では動物の「家鴨」の形がイメージされ、それが跳んだり跳ねたりしてしまい、「あ」「ひ」「る」という個々の字形への配慮が消えてしまいます。イメージはどんどん膨らんで、動物園や物語へと発展しおしゃべりが始まり、文字のとめ・はらいやまるみなんかどこかにいってしまいます。 これが、「ひるあ」とか「るあひ」に文字の順番を組み替えると、おもしろいことに字形がよくなります。手本をよく見ないと文字の配列がわかりませんし、具体的なイメージがない分、字形に対する注意を思いおこしやすいのでしょう。 鉛筆の持ち方も同じです。線の練習の時は良い持ち方で書けるのですが、文字になると急に悪くなります。日頃の習慣が出てしまうのでしょう。それに、ひらがなはいろいろな方向の線の組み合わせですから正しい持ち方では対応できないのです。 指先の器用さが鉛筆を持つことに対応出来る前から文字を書かせ、筆順に対する理論的な理解ができるだけの知的な発達がないのに、つまり入学前に“勉強をさせる”から、持ち方も筆順も変なくせがつくといわれる、小学校の先生の言い分もわからなくもありません。 そうはいっても、現実には幼児期に文字を書かざるをえない事情も、教えなくても見よう見まねで字を書いてしまうという現象もあるのですから、書くことを否定するより積極的な書き方の研究をするべきでしょう。 |
| (7)左利きについてー左手で書いてはいけないの?- (年長) ・子どもが左利きなので、家でドリルなどをしていても運筆の途中、左手が影になって書きにくそうにしている。 (ほとんどのドリルが右利き用なので)左利きは不利何のでしょうか? (年少) ・鉛筆の持ち方左右両方の手をつかっているので書く手がどちらになるかわからない。無理にきょう正するつもりは ないのですが左ききへの指導や問題点などしりたい。子どもが楽しく学べる指導をしていただきたい。 【コメント】 左利きを直すべきかどうかについては、それぞれの家庭によって異なって当然ですが、現時点では、 文字を書くことに関して左利きの子どもたちへの配慮がほとんどなされていません。 ですから、文字の習得の初期においては保護者が各自で対策を立ててやる必要があります。 それは左利きの子どもに右手で書かせる場合も同じです。文字自体は左手では書きにくい形や筆順になっています。右利きの子どもと同じような指導は好ましくありません。けれども、左利きの子どもへの指導マニュアルも、ワークブックもありません。 左利きの子が右手で文字を書くようにさせられたことで非常な苦痛を味わったということはよく聞きます。 けれども、左利きの子どもたちが文字をきれいに書くための方法とか、精神的な苦痛を与えずに右手にかえる方法などは 考えられていないことこそ困ったことです。 ネットで左利き用のグッズをいろいろと捜してみましたが、文字教材は大人向けのものが1種類のみ。 子どもたちのためのものはありませんでした。 今後の課題として早急に対処させてもらいます。 左利きの子どもさんをお持ちの方、ご自身が左利きの方のご意見をいただきたいと思います。
|