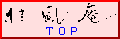『いろはDE書』
11:00―20:00(最終日は16:00まで)
☆所 アーバンビューグランドタワー公園空地内
Gallery(ギャラリー) G
(広電白島線縮景園前電停前)
|
桂風庵主の初の個展です。 全作品が「いろは歌」。 みなさまおなじみの「いろはにほへと・・・あさきゆめみしゑひもせす」です。 今回は表現を優先したかったので、手習い歌、文字の学習教材としての「いろは歌」を素材としました。もちろん「いろは歌」にも、いくつかの解釈がありますが、今回は内容と表現の関連は考慮していません。 「いろは歌」を全作品の共通の語句として、さまざまな表現の調和を念頭に置きました。 制約された空間と時間の中で、私がどのような表現を選択するのか、自分を水際へ追いつめてみたいという、やや自虐めいた気持ちもありました。そうすることで、自分にとっての書の存在がよりクリアになると思ったからです。 もっとも、そんな思いはすぐに飛んでしまい、塩出ワールドの構築にのめり込んでしまいました。 こんなにワクワクする世界に招待してくれた「書」にひたすら感謝。 そして、それが多くの人々との縁を結んでく れたことに、またまた感謝。 そんな塩出智代美の 『SHOわーるど』をご覧ください。 |
|
【会場風景】 〝ギャラリーG〝は近代的な建物で、スペースの仕切りも個性的。 全面ガラス張りなのは、通りすがりの人々に外からも楽しんでもらえるようにとの配慮からとか・・・ 確かに、中での展示は通路からもまる見え。   でも、中の作品が小さいと「何か飾ってあるらしい」ということしかわかりません。 屋外から見て楽しんでもらうためには、かなり大きな作品でなくてはなりません。 ということで、次のような作品ができました↓ |
|
【ガラス壁面を額に見立てる】 正面のガラスの仕切りは細長い額縁のよう。これをうまく生かして、通りがかりの人に見てもらうことを考えました。 通りすがりの人の目にも止まります。 半透明の料紙なので、中の作品もチラリと見えてGOOD! ↓   ちょっと近づいてみると・・・↑  
お昼休みに通りがかった人たちは、池の中をのぞき込んだり、垂れ幕のような作品を見上げたり、隙間から中をのぞいたり・・・ 会場内にいる私は、動物園の檻にいるサルになった気分でした。「ねぇ、こっちむいてよ~ 」 |
|
【1階の作品】 これが今回最大の作品 パネル4枚仕立てで全体の大きさは縦3メートル×横3メートル! 大きすぎて正面から撮影出来ませんでした。 真っ白い会場に黒の料紙。文字は金。インパクトはあります。 洋紙にアクリル絵の具で書いています。画仙紙に濃墨で書いたような質感を出すのに苦労しました。  どれだけ大きいかということを、展示準備の写真でお見せします。↓   |
|
【1階の作品 その2】 これが今回最長の作品 条幅(137㎝×34㎝)3枚継ぎの三部作。全長4.5㍍! 会場の天井の高さを活かして、篆書、隷書、かなのコンビネーション。 お互いの調和に気を配りました。 隷書作品は初体験。最後まで臨書をしましたが、納得ゆかず・・・  作品の一部を拡大↓ 2階から見下す↓   |
|
【1階の作品 その3】 全紙(68㎝×137㎝)2枚1セットの作品。  作品を拡大↓   「漢字かな交じり書」は漢字とかなの書道二分野のコラボレーション。 この作品は楷書、行書、草書、隸書、篆書すべての書体のコラボレーション。 書道用語では「破体書」ともいいます。 これも「いろは歌」です。右が前半「いろは・・・つねならむ」左が後半「うゐの・・・ゑひもせす」 |
|
【1階の作品 その4】 半切作品。2枚でひと組。 篆書を散らし書きにした作品。かなの持ち味を隷書作品に。和風と中国風のコラボレーション(^^;)  部分拡大→   |
|
【2階の作品 その1】    これらの作品の背景の料紙は一昨年前の文教女子大学の卒業生、坪田さんの手作り料紙。 私が仮名を指導した学生です。 彼女は自作の料紙に直接書きましたが、私は台紙として使用。 同じ版木を使用した、色違い三部作。 右上は料紙を縦に使っています。 |
| 【2階の作品 その2】 扇面2枚を貼り込んだ屏風です。 この扇面は料紙作家近藤富枝先生のもとで制作されたものです。平安時代の、破り継ぎという製法で、何枚もの華麗な料紙を組み合わせて、扇面に仕立ててあります。 平安時代でも、かなを書く料紙としては最高のものでした。 通常はこの扇面に和歌を直接書いて、それを表装するのですが、今回は背景となる紙の方に文字を書きました。 最近はこのようなものは見られませんが、歴史的には諸処みられます。 扇面の色調にマッチする台紙と文字構成にはかなり苦慮しました。    |
|
【階段を降りながら見る作品】  階段のうしろの細長い壁面を有効に利用してみました。 階段を下りるときに、自然に目に入るので、意外とギャラリーの印象に残ったようです。 |
|
【会場風景】    2階はロフトになっています。下から見上げたり、上から見下ろしたりすると、作品もまた違って見えます。 日が暮れて、外の木々がライトアップされると、外から見える会場内は幻想的。ガラスや池に反射した作品が不思議な世界をつくり出しました。 予期せぬライト效果が・・・ 
  |
会場を独占して、おもいのまま、やりたい放題!! なんてゴージャス!!まさに個展の醍醐味。
制作は、とても楽しかったです。
その後は他力本願!
多くの皆さまの協力があったから出来たことです。
本当になんとお礼を言えばよいのやら・・・ ただただ感謝です。 m(__)m
3月とは思えぬ寒さの中をご来場くださいました皆さま、ありがとうございました。
今後とも宜しくご支援下さいませ。